「Webサイト」と「ホームページ」はどう違う?制作現場での正しい使い分け方を解説
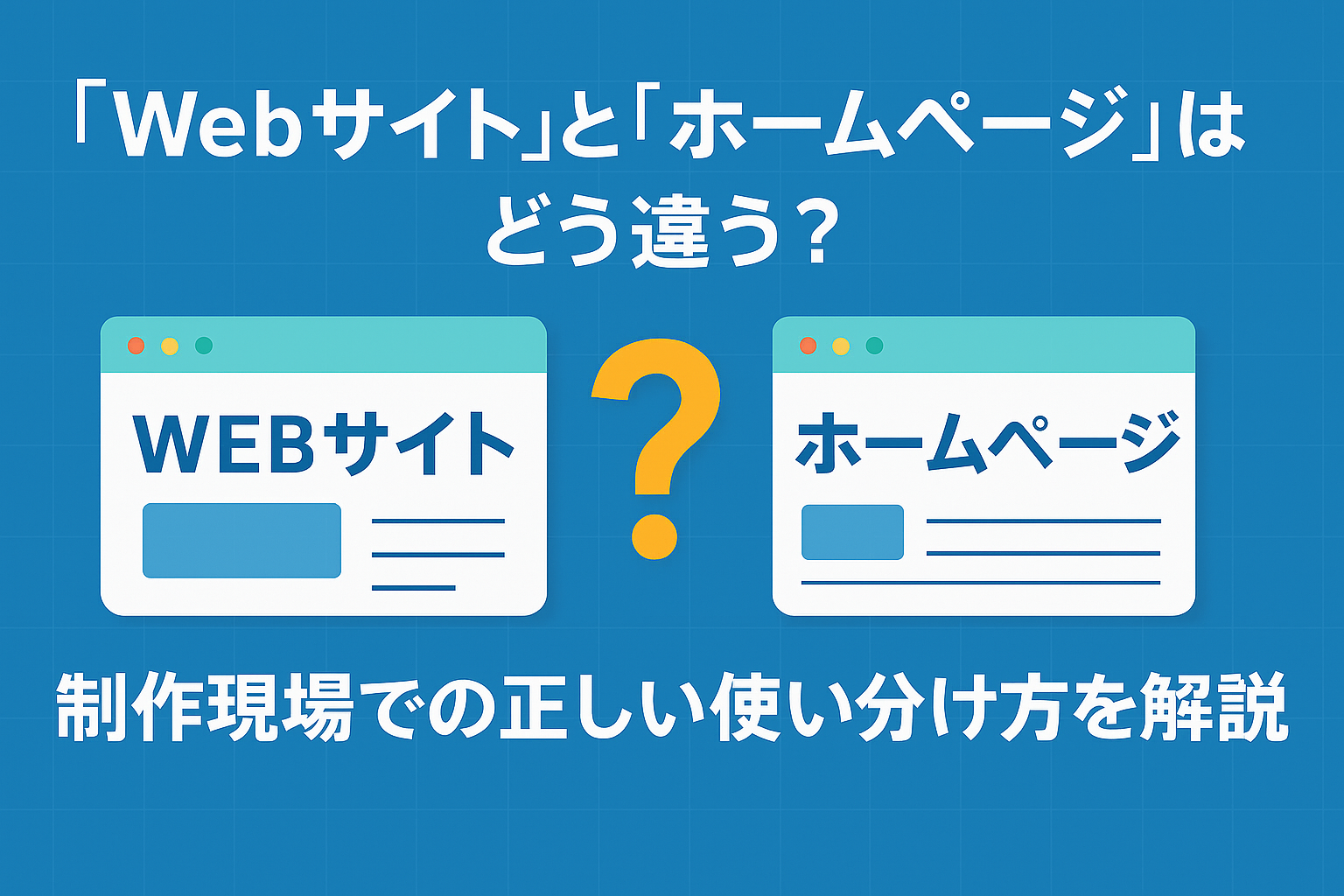
「Webサイト」と「ホームページ」、あなたはこの2つの言葉を正しく使い分けていますか?制作現場にいると、社内やクライアントから「このホームページどうなってる?」なんて聞かれることも多いはず。でも、実はこの2語には明確な違いが存在します。本記事では、両者の意味と使い分け方を、制作・運用の現場にいる方がすぐに実践できるよう、シーン別にわかりやすく整理して解説します。
Webサイトとホームページの基本定義
Web業界にいると、当たり前のように飛び交う「Webサイト」と「ホームページ」ですが、実はこの2つ、厳密にはまったく別の意味を持つ言葉です。
それなのに、現場ではわりとラフに、というか曖昧に使われることも多いですよね。
えっ、どっちも同じ意味じゃないの?ってなりますよね。
さて、まずはそれぞれの定義をしっかり整理していきましょう。
Webサイトとは?定義と構造
「Webサイト」とは、複数のWebページが集まった“情報の集合体”を指します。
具体的には、HTMLやCSSなどのファイルで構成され、URLを通じてインターネット上で閲覧できるものです。たとえば、会社案内、製品紹介、採用ページなど、複数のページをまとめて「企業のWebサイト」と呼びます。
技術的には、ドメイン配下で動作する複数のHTMLドキュメントや画像、スタイルシート、JavaScriptなどで構成されており、それらが論理的にリンクされている構造です。
つまり、「1つのテーマのもとにまとめられた、複数ページでできた情報群」がWebサイトというわけですね。
これが、クライアントが言う「全部が見られるやつ」であり、発注の対象になるものです。
ホームページの3つの意味とは
一方で、「ホームページ」には、状況に応じて3つの意味があります。これが混乱の元でもあります。
1つめは「Webサイトのトップページ」です。
この定義は、英語でいうところの“homepage”が該当し、サイトの玄関口・最初に表示されるページを意味します。
たとえば、「https://example.com/」というURLにアクセスしたときに表示されるページ。それがホームページです。
2つめは「ブラウザのスタートページ」。
これはChromeやSafariなどのWebブラウザを起動したときに最初に表示されるページのことで、Googleを設定している人も多いですよね。これは「ユーザー個人の入り口」という意味合いになります。
3つめが、日本独特の「Webサイト全体をホームページと呼ぶ」使い方です。
これが最も一般的に広まっており、「うちのホームページ見てね」というセリフに表れています。
この3つを同時に知ると、ちょっと頭こんがらがりますね。
なぜ混同されるのか?日本語ならではの事情
この混同の背景には、日本のインターネット黎明期にあった“言葉の広まり方”が関係しています。
1990年代、個人が初めてインターネットに触れたとき、「ホームページを作ろう」という表現が一気に広まりました。
その頃、HTMLで1枚のページを作るだけでも「自分のホームページ」と呼んでいたのです。
結果として、「ホームページ=Web上にある自分の情報ページ=全部」という認識が根付いたのが日本独特の進化だったわけです。
ちなみに、英語圏では「homepage」はトップページのことを指すのが一般的で、Webサイト全体のことを「website」と表現します。
つまり、海外と日本で同じ言葉でも指している内容が違うというややこしさがあるんですね。
《エピソード》ホームページって全部のこと?
筆者がWeb業界に入ったばかりのころ、あるクライアントとの打ち合わせでこんなことがありました。
「御社のホームページをリニューアルするということで、まずトップページのデザインからご提案を…」と話したところ、
「いや、ホームページ全部でしょ?」ときっぱり返されたんです。
そのとき筆者は、トップページのことを「ホームページ」と呼び、全体は「Webサイト」と言うものだと習っていたので、思わず一瞬フリーズしました。
実際はクライアントが言っていたのは「Webサイト全体」のことであり、こちらの認識とのズレが発生していたわけです。
この経験から、筆者は「言葉の使い方は、相手の文化や認識次第」と身に染みて学びました。
業界にいるとつい正しい言葉を使いたくなりますが、それが必ずしも伝わるとは限らないんですよね。
「違いがある」と困る現場のリアル
言葉の使い方ひとつで、制作現場が混乱することは少なくありません。
「ホームページ」と「Webサイト」をきちんと区別しないまま話が進むと、後から「え、それ含まれてると思ってた」「いや、それは別料金です」といったズレが起きがちです。
ここでは、制作側とクライアント側、それぞれに起こる“あるあるな混乱”を紹介します。
制作側の混乱例:見積りが狂う、設計もブレる
まずは制作者の立場から。
「ホームページを作ってください」と言われたとき、それが“トップページ1枚”のことなのか、“10ページ構成のWebサイト全体”なのかで、設計・工数・価格は大きく変わります。
たとえば、トップページだけならデザインも構造も比較的シンプル。コンテンツ量も限られるため、作業ボリュームは明確です。
でも、それがWebサイト全体になると話は別。
複数の下層ページ、共通ナビゲーション、フォームの実装、CMSの組み込み、さらにはモバイル最適化まで、一気に仕様が増えてきます。
にもかかわらず、「ホームページ作成5万円くらいでお願いできる?」なんて言われると、見積もりが大事故になります。
それって、ランチ代でコース料理頼むみたいな感覚かもしれません。
また、設計段階でも同様です。
「ホームページにこの情報も載せたい」と後出しされて、気づけば5ページ分の構成になっていることも。
こうなると、デザイナーもコーダーも最初に決めた設計を全部見直す必要が出てきます。
クライアント側の誤解:「頼んだのはホームページだけ」問題
もちろん、制作側だけが困っているわけではありません。クライアント側にも戸惑いや誤解はあります。
特に、非IT業界の方にとっては「ホームページ=会社のWebの全部」という認識が根強くあるため、「トップページだけ作ってほしいなら、そう言って」と思っているケースもあるのです。これはもう、文化の違いとしか言いようがありません。
実際、筆者も過去に「ホームページを作ってもらったけど、会社情報のページがないのはどうして?」と問い合わせを受けたことがあります。
ちゃんと確認してなかったんじゃ…ってなります。
クライアントから見れば、Webの知識がないからこそ「ホームページ」とざっくり頼むわけで、そこに制作側の細かい用語が噛み合わないと、後で不満やトラブルになってしまいます。
《エピソード》「トップだけ?それとも全部?」
ここで、筆者の知り合いであるWebディレクター・田中英明さん(仮名)の事例をご紹介します。
田中さんが担当した案件では、クライアントから「ホームページをリニューアルしたい」という依頼が入りました。
事前にヒアリングを重ねたところ、どうやらデザインの話が中心だったため、「ああ、トップページの刷新だな」と判断して見積書を提出。金額は20万円。
ところが、初回のワイヤーフレームを提出した段階で、クライアントから「会社概要ページと商品紹介ページは?」と聞かれ、田中さんは冷や汗。
実際には全10ページのWebサイトリニューアルを依頼されていたのです。
結局、工数やスケジュールを再調整することになり、見積額も当初の倍近い40万円に。
クライアントも「そんなに高くなるとは思ってなかった」と不満を漏らしていたそうです。
この出来事以降、田中さんは「“ホームページ”という言葉が出たら、まず“それってトップページだけですか?”って必ず確認するようになった」と言っていました。
言葉があいまいなままだと、制作側とクライアント側、どちらにとっても“誤解が前提”で進むリスクがあります。
こうしたリアルなトラブルは、現場でよくあるだけに、「言葉の定義」ってすごく大事なんです。
次章では、そんな誤解を避けるために、具体的にどう言葉を使い分けて説明すればいいか、場面別の工夫をご紹介します。
制作・会話でのおすすめ使い分け術
ここまで読んでくれた方なら、「Webサイトとホームページ、やっぱり違うんだな」と思っているはずです。
でも、知識を得ただけでは終わらせませんよ。
この章では、実務や会話の中で“相手にちゃんと伝える”ための使い分け術を紹介します。
どんなに定義が正しくても、伝わらなければ意味がない。
筆者が現場で実践してきたテクニックを交えて、具体的な言い回しや表現のコツを紹介していきます。
実務でどう言い分ければ伝わる?
まず大前提として、相手によって言葉の解釈は違います。
だからこそ、制作サイドでは「正しい言葉」と「伝わる言葉」のバランスを意識しないといけません。
たとえば、上司とのやりとりで「このWebサイトの構成ですが…」と言ったとしても、相手が非エンジニアだと「?」となってしまうこともあります。
逆に、社内のエンジニアやデザイナー相手なら、「ホームページ」という言葉は曖昧すぎて設計がブレる可能性も。
つまり、“誰に・何のために”話しているかによって、適した用語は変わってくるということです。
これを最初に学んでいたら、苦労減ったのに〜!
クライアント対応で重要なのは、「伝えるためにあえて崩す勇気」です。
筆者はあくまで“伝える目的”を最優先にして、必要なら正しさよりも分かりやすさを選びます。
【場面別】おすすめの言い回し・使い分け
では、実際にどんな場面でどう使い分ければいいのか?
具体例で紹介していきます。
● 資料や設計書:Webサイトで統一
ドキュメント上では、用語の曖昧さはトラブルのもと。
「Webサイト」という言葉で統一し、ページ構成やコンテンツマップに反映させましょう。
たとえば:
- ✕「ホームページ構成案」
- ○「Webサイト構成図」
と表記するだけで、プロジェクト関係者全員が誤解なく話を進めやすくなります。
● 会話や打ち合わせ:ホームページで柔らかく
対話の中では、相手が非IT系なら「ホームページ」のほうが断然伝わります。
特に年配の方や、Webに詳しくないクライアントには、「Webサイト」と言ってもピンと来ません。
例:
- 「御社のホームページに、採用情報を追加する形ですね」
- 「ホームページ全体のリニューアルをご希望ですか?」
これなら自然に話が進みやすいです。
● IT職種の人:Webサイトが基本
逆に、デザイナーやエンジニア、マーケターなどIT職の方には、「Webサイト」という用語で。
「ホームページ」という言葉は誤解を生みやすいので、設計や仕様の話ではなるべく使わないのがベターです。
相手によって言葉を選ぶのは、営業でもありますよね。
《エピソード》営業同行での“言い換えリクエスト”
筆者がまだ中堅くらいだったころ、営業チームに同行してクライアントとの打ち合わせに参加したときのこと。
クライアントは不動産系で、Webに詳しいわけではありませんでした。
打ち合わせの直前、営業の佐藤麻衣子さん(仮名)にこう言われました。
「○○さん、“Webサイト”って言わないで、“ホームページ”で話してくれる?あっちの社長さん、“Webサイト”って言葉苦手っぽいから」
正直、「え、ここでそれ言う!?」と思いましたが(笑)、言葉ひとつで距離感が変わるのも事実。
その場では、すべて「ホームページ」という表現に言い換えて会話を進めました。
結果として、クライアントの反応も良く、追加発注までいただけたというオチ。
あの時ほど「伝えるって、正しさじゃなくて相手目線なんだな」と実感した瞬間はなかったです。
専門的な言葉を知っていても、それを誰にどう伝えるかが、プロとしての力量です。
「正確さ」だけにこだわるよりも、伝わることを優先する。
それが結局、一番スムーズなプロジェクト進行にもつながるんですよね。次章では、この“言葉の使い分け”がSEOにどう影響するのか。
検索ワードとしての「ホームページ」「Webサイト」の使い分けについても触れていきます。
「ホームページ」のSEO的な扱い方
ここまでは、“言葉の意味”や“使い方”についてお話してきましたが、この章では視点を少し変えて、「ホームページ」と「Webサイト」がSEOでどう扱われているのかに焦点を当ててみます。
制作だけじゃなく、集客やマーケティングに関わる方にもめちゃくちゃ大事な話です。
特に、Web担当者やコンテンツ設計をする人にとっては、言葉選びがそのまま検索順位やアクセス数に直結します。
筆者もコーディングだけでなくSEO案件にも携わることがあるので、その中で気づいたこと・リアルな事例も交えてご紹介します。
検索ボリュームは「ホームページ」の方が多い
SEOでまず見るべきは検索ボリューム。
つまり、ユーザーが実際にどの言葉を検索しているかということです。
GoogleキーワードプランナーやUbersuggestなどで調べてみるとわかりますが、
「Webサイト」よりも「ホームページ」の方が圧倒的に検索数が多いんですよね。
たとえば――
- 「ホームページ 作成」:月間約27,000件
- 「Webサイト 作成」:月間約6,000件
この差、約4倍以上。
つまり、多くの人は「Webサイトを作りたい」と思っていても、検索では「ホームページ」と入力しているということです。
そんなに違うの!?ってちょっと驚きました。
この背景には、「ホームページ」という言葉が一般的に浸透していること、日本語環境での“検索習慣”が根強いことがあります。
要するに、「通じる言葉=検索される言葉」なんですね。
コンテンツ設計やタイトルでの使い分け例
じゃあ、SEO的には「ホームページ」を全面的に使えばいいのか?
というと、そう単純な話でもありません。
たとえば、以下のようなシーンでは言葉を使い分けた方がベターです。
① ブログ・記事タイトルには「ホームページ」
→検索流入を狙うために、「ホームページ」の方が有利。
例:「ホームページ作成の流れ」「ホームページとWebサイトの違い」
② 専門コンテンツ内では「Webサイト」も使う
→ページの中での用語の正確さや、読者のレベルに応じて「Webサイト」を登場させる。
例:「Webサイト構造の基本」「サイトマップ設計におけるWebサイト分類」
このように、「入り口では“ホームページ”」「中では“Webサイト”」という設計が有効です。
目的地にたどり着くための正しい道筋があるという点で、ユーザーを“自然に導く”ための動線設計は、コーディングとちょっと似てますよね。
実際の検索ユーザーを想定したキーワード設計
SEOで成果を出すには、“検索する人の気持ち”を想像するのが何より大事です。
たとえば、以下のようなユーザー像が考えられます。
- 「初めて自分の店のサイトを作ろうと思ってる」
→検索キーワード:「ホームページ 作り方」 - 「社内でサイトのリニューアルを検討中」
→検索キーワード:「ホームページ リニューアル 費用」 - 「業者に頼みたいけど、どう比較すればいい?」
→検索キーワード:「ホームページ制作会社 比較」
これ、全部「Webサイト」じゃなくて「ホームページ」で検索されるパターンなんです。
一方、マーケターやITリテラシーの高い人は、
「Webサイト 戦略」「Webサイト UX 改善」などで検索することもあります。
つまり、ユーザーの知識レベルに応じてキーワードを出し分けるのが、SEOでは鉄則です。
言葉ひとつでターゲット変わるのって、なんだか面白いです。
《エピソード》「Webサイト」で失敗、「ホームページ」で流入激増
筆者の知り合いに、SEOディレクターの佐藤美咲さん(仮名)がいます。
ある企業ブログで「Webサイト制作のポイント」という記事を作ったんですが、全然検索にヒットしなかったそうです。
その後、タイトルと見出しを「ホームページ制作のポイント」に変えて再公開したところ、なんと3週間でアクセスが6倍以上に増加。
「検索ユーザーの言葉で書くことがこんなに違うんだって、身をもって実感した」と話していました。
実はこの企業のメインターゲットが中小企業の経営者層で、Webに強いわけではなかったんです。
つまり、「Webサイト」は届かない言葉だったんですね。
SEOにおいては、“正しい言葉”より“使われている言葉”が勝ちます。
そして、その“使われている言葉”は時代や層によって変わるもの。
「ホームページ」を使うのがダサいと思われがちですが、検索で選ばれる言葉なら、それが正解なんです。
まとめと感想|伝えるための選び方を
「Webサイト」と「ホームページ」、この2つの言葉の違いにここまでしっかり向き合った方は、きっともう“なんとなく”では使えなくなっていると思います。
でも、誤解しないでほしいのは、「間違えないこと」がゴールじゃないってことなんです。
筆者がここで一番伝えたいのは、“言葉の選び方ひとつで、伝わり方も、相手との関係も変わる”ということ。
つまり、「違いを知ること」=「相手との距離を縮めること」なんですよね。
用語に“正解”はあっても、“最適解”は人それぞれ
ここまでの章で紹介してきたように、「Webサイト」と「ホームページ」には確かに明確な定義の違いがあります。
でも、現場では「定義どおり」に話すことが、必ずしも正解とは限りません。
IT職やエンジニアの間では「Webサイト」がしっくりくるけれど、非ITの方には「ホームページ」と言った方が伝わる。
シーンによって使い分ける力が、これからのWeb担当者や制作者には求められていると思います。
“わかる言葉で話す”って、すごくやさしいことですよね。
会話の中で少しだけ表現を変えるだけで、相手がすっと理解してくれる。
その瞬間って、ちょっと嬉しいんですよね。
“正しい”だけでは届かない。大切なのは“伝わる”こと
筆者がWebの仕事を続けてきて、一番実感しているのはこれです。
「この用語、正しくないけど、あえて使うほうが伝わるな」
そう思った瞬間に、“プロとしての表現力”って試されてるんだなと感じます。
クライアントとの信頼関係や、社内でのスムーズな意思疎通。
それを築くために、言葉の選び方は“配慮”であり、“戦略”でもあるんです。
《エピソード》納得できた、あの使い分け提案
ある日、筆者が担当していたリニューアル案件で、クライアントからこんな相談を受けました。
「社内で“ホームページを刷新する”って言ってるんだけど、うちのマーケ部は“Webサイト”って言ってて、なんかチグハグなんですよ」
そこで筆者は、こう提案しました。
「外向けの資料では“ホームページ”と書いてください。でも、内部向けの設計や進行管理では“Webサイト”で統一しましょう」
その理由も添えて、
「ホームページは検索でも強いし、一般の人にも伝わりやすい。だけど、制作中の仕様や指示は“Webサイト”の方がズレません」
と説明しました。
クライアントの担当者・川村裕子さん(仮名)は「それなら両方納得できる」とすごく喜んでくれて、結果的にプロジェクトもスムーズに進みました。
このとき、「正しさ」と「伝わりやすさ」、どちらも大切にした提案がちゃんと届いたことに、筆者自身も満足感がありました。
“言葉を選ぶ”って、思ってたよりクリエイティブな仕事かもしれません。
最後に|言葉は“使い方”がすべて
言葉って、道具なんですよね。
正確に研ぎ澄ませば強力なツールになるし、扱いを間違えれば誤解や混乱の原因にもなる。
だからこそ、今回の記事を通して、「Webサイト」「ホームページ」という用語が持つ意味、背景、使い分けのコツを少しでも伝えられたなら嬉しいです。
そして何より、読者のみなさんが誰かとやりとりをするとき、相手の理解に寄り添った“伝え方”を選んでくれることを願っています。
それができる人は、間違いなく“信頼されるWebの人”です。
ここまで読んでくれて、ありがとうございました。
次はぜひ、あなた自身の言葉で「Webサイト」と「ホームページ」を使い分けてみてください。
